1月に入って、寒さ厳しい日が多くなりましたね。
寒くなると空気が乾燥して、風邪、インフルエンザになる人が増えてきます。
こんな時期だから、生姜の効能などを書いていきます。

まず最初に、「しょうが」の入った料理を食べたり飲み物を飲むと身体の中からぽかぽかと温かくなるのがわかりますよね。
「しょうが」には血行を良くして身体を温める効能があるということは、昔から多くの人に知られています。
日本では寿司の薬味や料理の下味など食材として使われることが多い生姜ですが、海外ではハーブやクスリのように用いられることもあります。
生姜の効果
生姜の持つ効果や効能としてよく知られているのは、血液の循環をスムーズに行えるように働きかけ、身体を温めてくれるというものです。
その他には、あまり知られていないものもありますが、吐き気をとめる効果もあるといわれています。
はっきりとした効果が確かめられてはいないようですが、東洋医学では乗り物酔いに効果があるともいわれて船やバスなどの乗り物に乗る際に利用されていることもあります。
また、身体の不調は、体内に不要なものや、身体に負担となるものがあるために起こると考えられることもあります。そのため、しょうがの胃や腸に対する刺激で消化機能を促進させたり、発汗作用や循環機能の活性化などからその不要なものを取り除く解毒の効果があるとして、しょうがの絞り汁やすりおろしたものが使われることもあります。
同じように、不要なものを取り除き体内の様々な機能がスムーズにバランスよく働くようにすることから、下痢や便秘の解消にも効果があるといわれています。
生姜を食用として取り入れる際には、生の生姜で一日小さじ1杯程度乾燥生姜の場合は1〜4gを目安に摂取するとよいといわれています。
生姜には色々健康に役立つ成分が含まれているといわれていて、欧米ではハーブとして生姜を使っていることも多いようです。
また、中国やインドでは古くから伝わる伝統医学の中に必ずといっていいほど生姜は利用されています。
イギリスでぺすとが流行った時には、当時のイギリス国王ヘンリー八世が生姜の成分がぺすとの予防に役立つとして国民に生姜を食べるように勧めました。
その後、イギリスを始めとする欧米では、ジンジャーブレッドやジンジャークッキーが頻繁に食べられるようになったようです。
生姜自信にはぺすとなどをやっつける効果はありませんが、体内の血行を促進したり循環機能を高める効果があります。
ですから、生姜を食べることで身体が外から入ってくる異物に対すして防衛機能が高まり、様々な疾病を要望する効果があると考えられます。また、中国で「生姜」は、漢方には欠かせない存在として広く活用されています。
生姜だけで効果を出すように利用されるのではなく、他の漢方薬と組み合わせて使われます。
生姜の持つ消化吸収を助け、循環機能を活性化させる働きを利用することで組み合わせた他の漢方薬の吸収を助け効果や効能を引き出して効果を高めるという作用を狙って利用されることが多いようです。
生姜の成分
しょうがには独特の刺激を持つ香りや風味があります。生姜に含まれる成分には、生姜の皮のすぐ下の部分から抽出される精油に含まれる成分と、しょうがの澱粉質に含まれる成分があります。
澱粉質に含まれる成分には独特の香りや風味のある「オレオレジン」という成分があり、オレオレジンの中には、殺菌作用や抗酸化作用のある「ショウガオール」や「ジンゲロール」という成分が含まれています。
ジンゲロールには、吐き気を抑える「セロトニン」を抑制する働きがあることがわかってきました。また、精油にはジンギベレン・ボルネオール・ファルネセンなど30種類以上の成分が含まれています。
代表的なものには、クルクミンやリモネンがあります。
精油に含まれる成分は生姜の皮のすぐ下にあるため皮をむいたしょうがには含まれていないことが多くあります。
乾燥させてしまうと、精油に含まれる成分の多くは化学変化し、他の成分に変わってしまったりなくなってしまったりすることもあります。
特に生姜独特の爽やかな香りは失われやすいため、乾燥生姜の香りは弱いものがほとんどです。
風邪の予防に効果的
風邪は体力や免疫力が低下している際にかかりやすいといえます。
そのため、風邪っぽいときには、身体を温め循環機能を高めることで風邪が悪化するのを防ぐことができます。
また、発熱がある場合には、生の生姜をすりおろし、蜂蜜やレモンと一緒にお湯でわって飲むと発汗作用によって汗をかき、熱を下げる効果があるといわれています。
○美味しい生姜湯の作り方
1)使い残しの生姜を、おろし金でおろし、リードで包み絞る。
◎茶こしでこしても良い。
2)生姜汁に、蜂蜜・レモンの絞り汁を入れ、あついお湯を注ぐだけ。
◎のどが痛い時や熱っぽい時に体が温まり風邪が吹き飛んでしまうそうです。
寒くなると空気が乾燥して、風邪、インフルエンザになる人が増えてきます。
こんな時期だから、生姜の効能などを書いていきます。

まず最初に、「しょうが」の入った料理を食べたり飲み物を飲むと身体の中からぽかぽかと温かくなるのがわかりますよね。
「しょうが」には血行を良くして身体を温める効能があるということは、昔から多くの人に知られています。
日本では寿司の薬味や料理の下味など食材として使われることが多い生姜ですが、海外ではハーブやクスリのように用いられることもあります。
生姜の効果
生姜の持つ効果や効能としてよく知られているのは、血液の循環をスムーズに行えるように働きかけ、身体を温めてくれるというものです。
その他には、あまり知られていないものもありますが、吐き気をとめる効果もあるといわれています。
はっきりとした効果が確かめられてはいないようですが、東洋医学では乗り物酔いに効果があるともいわれて船やバスなどの乗り物に乗る際に利用されていることもあります。
また、身体の不調は、体内に不要なものや、身体に負担となるものがあるために起こると考えられることもあります。そのため、しょうがの胃や腸に対する刺激で消化機能を促進させたり、発汗作用や循環機能の活性化などからその不要なものを取り除く解毒の効果があるとして、しょうがの絞り汁やすりおろしたものが使われることもあります。
同じように、不要なものを取り除き体内の様々な機能がスムーズにバランスよく働くようにすることから、下痢や便秘の解消にも効果があるといわれています。
生姜を食用として取り入れる際には、生の生姜で一日小さじ1杯程度乾燥生姜の場合は1〜4gを目安に摂取するとよいといわれています。
生姜には色々健康に役立つ成分が含まれているといわれていて、欧米ではハーブとして生姜を使っていることも多いようです。
また、中国やインドでは古くから伝わる伝統医学の中に必ずといっていいほど生姜は利用されています。
イギリスでぺすとが流行った時には、当時のイギリス国王ヘンリー八世が生姜の成分がぺすとの予防に役立つとして国民に生姜を食べるように勧めました。
その後、イギリスを始めとする欧米では、ジンジャーブレッドやジンジャークッキーが頻繁に食べられるようになったようです。
生姜自信にはぺすとなどをやっつける効果はありませんが、体内の血行を促進したり循環機能を高める効果があります。
ですから、生姜を食べることで身体が外から入ってくる異物に対すして防衛機能が高まり、様々な疾病を要望する効果があると考えられます。また、中国で「生姜」は、漢方には欠かせない存在として広く活用されています。
生姜だけで効果を出すように利用されるのではなく、他の漢方薬と組み合わせて使われます。
生姜の持つ消化吸収を助け、循環機能を活性化させる働きを利用することで組み合わせた他の漢方薬の吸収を助け効果や効能を引き出して効果を高めるという作用を狙って利用されることが多いようです。
生姜の成分
しょうがには独特の刺激を持つ香りや風味があります。生姜に含まれる成分には、生姜の皮のすぐ下の部分から抽出される精油に含まれる成分と、しょうがの澱粉質に含まれる成分があります。
澱粉質に含まれる成分には独特の香りや風味のある「オレオレジン」という成分があり、オレオレジンの中には、殺菌作用や抗酸化作用のある「ショウガオール」や「ジンゲロール」という成分が含まれています。
ジンゲロールには、吐き気を抑える「セロトニン」を抑制する働きがあることがわかってきました。また、精油にはジンギベレン・ボルネオール・ファルネセンなど30種類以上の成分が含まれています。
代表的なものには、クルクミンやリモネンがあります。
精油に含まれる成分は生姜の皮のすぐ下にあるため皮をむいたしょうがには含まれていないことが多くあります。
乾燥させてしまうと、精油に含まれる成分の多くは化学変化し、他の成分に変わってしまったりなくなってしまったりすることもあります。
特に生姜独特の爽やかな香りは失われやすいため、乾燥生姜の香りは弱いものがほとんどです。
風邪の予防に効果的
風邪は体力や免疫力が低下している際にかかりやすいといえます。
そのため、風邪っぽいときには、身体を温め循環機能を高めることで風邪が悪化するのを防ぐことができます。
また、発熱がある場合には、生の生姜をすりおろし、蜂蜜やレモンと一緒にお湯でわって飲むと発汗作用によって汗をかき、熱を下げる効果があるといわれています。
○美味しい生姜湯の作り方
1)使い残しの生姜を、おろし金でおろし、リードで包み絞る。
◎茶こしでこしても良い。
2)生姜汁に、蜂蜜・レモンの絞り汁を入れ、あついお湯を注ぐだけ。
◎のどが痛い時や熱っぽい時に体が温まり風邪が吹き飛んでしまうそうです。
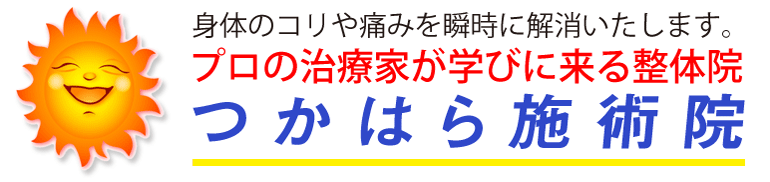




愛がガンを消した!? 奇跡は連鎖する by 韮沢香織 (04/19)
2015年1月スケジュール by 1 (01/11)
日曜日の朝にリフレッシュ!!高橋リサ先生と「朝ヨガと巨石パーク」 by マック (09/16)
日曜日の朝にリフレッシュ!!高橋リサ先生と「朝ヨガと巨石パーク」 by ちろる (09/16)