○プルーサーマルで使われるMOX燃料の危険性
これまでの日本の原子炉で使われてきたウラン燃料と、プルサーマルで使われるMOX燃料が放射能を比較すると、γ線でウランの20倍、中性子線で1万倍、α線で15万倍という、とてつもない危険性を持っています。
玄海原発に搬入するときに、もし事故があれば被害は想像を絶する大惨事になります。
さらに、これを玄海原発のような加圧四水型原子炉でプルサーマル燃焼させた場合、「使用後のMOX燃料(高レベル放射性廃棄物)がどれほど危険な中性子を出し、また発熱量がどれほど大きいか、中性子放出率は、19.7倍 発熱量は2.48倍。
MOX燃料がとてつもなく危険すぎて、再処理できないのです。
○玄海原発で生まれる使用済みMOX燃料はどこへゆくか
この超危険な使用済みMOX燃料は最後はどうなるか、九州の住民はきちんと知っておかなければなりません。
全国で拒否されてきた高レベル放射性廃棄物より、桁違いに危険な物質だからです。
プルサーマル計画の人体実験場と呼ばれる佐賀県玄海原発では、これが大問題となり、九州の住民と九州電力のあいだで、次のような順序でやりとりが行われました。
「プルサーマルを実施すれば」「危険性の高い 発熱量の大きな使用済みMOX燃料が発生する」
2004年7月13日「使用済みMOX燃料は発熱量が高くて、地下に埋められる温度に下がるまで約500年かかる」と核燃料サイクル開発機構が発表
「使用済みMOX燃料は玄海町から持ち出せないのではないか」と佐賀県が質問状
「使用済みMOX燃料は、種々の選択肢から電気事業者が決定していくものと考えられる」
というのが国の方針―と九州電力が回答(計画未定)(電力会社と国といずれが責任か)
「使用済みMOX燃料は当分、サイトの使用済み貯蔵プールに保管しておく
原子力文化振興財団のプルサーマル広報用パンフ(きわめて無責任な計画)」
「第二再処理工場で処理する」関西電力 (100%不可能な計画)
「使用済みMOX燃料の処分は、第二再処理工場か、直接処分か、原発サイト内保管か、何も決まっていない。責任主体も決まっていない。
このような無責任な計画では、地元民はプルサーマルを絶対に受け入れられない。
「六ヶ所村。再処理工場の運転を強行するための口実(看板)にすぎない。
真相は「プルトニウムの利用先がどこにもない」
「高レベル放射性廃棄物の最終処分場がどこにもない」ということである
ここにある「使用済みMOX燃料を再処理する」計画(たとえば六ヶ所村第二歳処理工場)は100%不可能な絵空事であります。結局核燃料サイクル開発機構が公言したとおり、発熱量が高いため、500年間は地下に埋めることもできず、サイト=玄海原発の敷地で保管しなければならない。
500年前といえば、室町時代に「応仁の乱」が起こって京の都が丸焼けになったあと、足利幕府滅亡に向かった時代であります。
織田信長が生まれる20年以上も前のことです。
そんなものを、佐賀県民が500年間、じっと保管していろというのです。
これから500年後に、九州電力は間違いなく、このホットな廃棄物を抱いて、この世から消えているでしょう。
そうなると、日本が廃墟となって、国があるかどうかもわからない。自民党なぞあるわけがありません。
だからこそ、これまで九州では、その死の灰の墓場をつくろうと、福岡県二丈町、長崎県対馬市、長崎県新上五島町、宮崎県南郷町熊本県天草郡御所浦町鹿児島県笠沙町鹿児島県奄美宇検村と、次々に高レベル放射性廃棄物最終処分場の誘致計画が持ち上がったのです。
次回につづく
これまでの日本の原子炉で使われてきたウラン燃料と、プルサーマルで使われるMOX燃料が放射能を比較すると、γ線でウランの20倍、中性子線で1万倍、α線で15万倍という、とてつもない危険性を持っています。
玄海原発に搬入するときに、もし事故があれば被害は想像を絶する大惨事になります。
さらに、これを玄海原発のような加圧四水型原子炉でプルサーマル燃焼させた場合、「使用後のMOX燃料(高レベル放射性廃棄物)がどれほど危険な中性子を出し、また発熱量がどれほど大きいか、中性子放出率は、19.7倍 発熱量は2.48倍。
MOX燃料がとてつもなく危険すぎて、再処理できないのです。
○玄海原発で生まれる使用済みMOX燃料はどこへゆくか
この超危険な使用済みMOX燃料は最後はどうなるか、九州の住民はきちんと知っておかなければなりません。
全国で拒否されてきた高レベル放射性廃棄物より、桁違いに危険な物質だからです。
プルサーマル計画の人体実験場と呼ばれる佐賀県玄海原発では、これが大問題となり、九州の住民と九州電力のあいだで、次のような順序でやりとりが行われました。
高レベル廃棄物とプルサーマル
「プルサーマルを実施すれば」「危険性の高い 発熱量の大きな使用済みMOX燃料が発生する」
2004年7月13日「使用済みMOX燃料は発熱量が高くて、地下に埋められる温度に下がるまで約500年かかる」と核燃料サイクル開発機構が発表
↓
「使用済みMOX燃料は玄海町から持ち出せないのではないか」と佐賀県が質問状
↓
「使用済みMOX燃料は、種々の選択肢から電気事業者が決定していくものと考えられる」
というのが国の方針―と九州電力が回答(計画未定)(電力会社と国といずれが責任か)
「使用済みMOX燃料は当分、サイトの使用済み貯蔵プールに保管しておく
原子力文化振興財団のプルサーマル広報用パンフ(きわめて無責任な計画)」
「第二再処理工場で処理する」関西電力 (100%不可能な計画)
【結論】
「使用済みMOX燃料の処分は、第二再処理工場か、直接処分か、原発サイト内保管か、何も決まっていない。責任主体も決まっていない。
このような無責任な計画では、地元民はプルサーマルを絶対に受け入れられない。
【なぜプルサーマルを強行しようとするのか】
「六ヶ所村。再処理工場の運転を強行するための口実(看板)にすぎない。
真相は「プルトニウムの利用先がどこにもない」
「高レベル放射性廃棄物の最終処分場がどこにもない」ということである
ここにある「使用済みMOX燃料を再処理する」計画(たとえば六ヶ所村第二歳処理工場)は100%不可能な絵空事であります。結局核燃料サイクル開発機構が公言したとおり、発熱量が高いため、500年間は地下に埋めることもできず、サイト=玄海原発の敷地で保管しなければならない。
500年前といえば、室町時代に「応仁の乱」が起こって京の都が丸焼けになったあと、足利幕府滅亡に向かった時代であります。
織田信長が生まれる20年以上も前のことです。
そんなものを、佐賀県民が500年間、じっと保管していろというのです。
これから500年後に、九州電力は間違いなく、このホットな廃棄物を抱いて、この世から消えているでしょう。
そうなると、日本が廃墟となって、国があるかどうかもわからない。自民党なぞあるわけがありません。
だからこそ、これまで九州では、その死の灰の墓場をつくろうと、福岡県二丈町、長崎県対馬市、長崎県新上五島町、宮崎県南郷町熊本県天草郡御所浦町鹿児島県笠沙町鹿児島県奄美宇検村と、次々に高レベル放射性廃棄物最終処分場の誘致計画が持ち上がったのです。
次回につづく
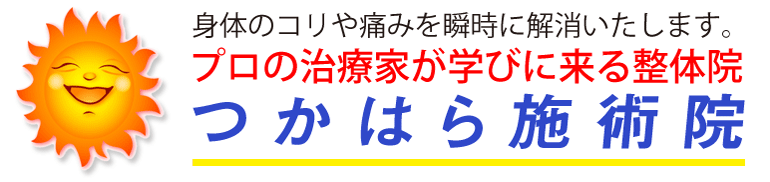





愛がガンを消した!? 奇跡は連鎖する by 韮沢香織 (04/19)
2015年1月スケジュール by 1 (01/11)
日曜日の朝にリフレッシュ!!高橋リサ先生と「朝ヨガと巨石パーク」 by マック (09/16)
日曜日の朝にリフレッシュ!!高橋リサ先生と「朝ヨガと巨石パーク」 by ちろる (09/16)