◆アメリカ・イギリス・フランス・ドイツが高速増殖炉に失敗した三つの理由
○高速増殖炉の技術的な危険性
□燃料のプルトニウムの毒性は、耳かき1杯で数万人を殺戮できるほど大きく、プルトニウム239は放射能が半減するまで2万4000年を要します。
□プルトニウム燃料は、ウランに比べて中性子を吸収しやすく(核分裂しやすく)、そのため核暴走が起こりやすく、核暴走のスピードも大きい。
フランスの高速増殖炉フェニックスでは、たびたび核分裂反応の暴走事故が発生し、出力上昇が100分の5秒という短時間に起こりながら、いまだに原因が解明されていない。
しかも、このような核暴走に対して、増殖炉では制御棒のほかに対策がなく、軽水炉に備えられている緊急炉心冷却装置(ECCS)さえ持たない。
□アメリカの高速増殖炉では炉心溶融事故を2度も起こしているが、わずかでも炉心溶融が起これば、プルトニウム濃度がその部分で高まり、急速な臨海反応によって原子炉が原爆化する可能性があります。
□燃料からから熱を奪うために使われるナトリウムは、金属パイプの壁一枚を隔てて、発電用として水蒸気を発生させる水と隣り合っています。このナトリウムは、水とはんのうして爆発炎上し、高温では空気とも反応して炎上する性質があります。
さらにナトリウムの腐食性が大きいので、配管事故が起こりやすく、伝熱パイプに亀裂が生じたり破損すれば、たちまち爆発に進展する可能性が高い。
イギリスでは1987年2月、高速増殖炉PFRで、蒸気発生器の細管ギロチン破断事故が発生し、40本の細管を連続破断させるドミノ倒し現象が起こり、かろうじて大惨事を免れた。
□軽水炉の水蒸気温度が300度であるのに比べて、増殖炉ではナトリウムが500度以上、水蒸気温度も500度近い温度であります。
この高温は、原子炉の停止時と運転時に、配管を大きく膨張・収縮させ、しかも伝熱パイプの内側と外側の圧力差は、130気圧ときわめて大きい。
このような厳しい条件にさらされるため、ごくわずかな金属欠陥があるだけで大事故を誘発しやすく、特に、高速増殖炉で使われる薄く大口径の配管は、地震に対してほとんど無力なのです。
○高速増殖炉の技術的な危険性
□燃料のプルトニウムの毒性は、耳かき1杯で数万人を殺戮できるほど大きく、プルトニウム239は放射能が半減するまで2万4000年を要します。
□プルトニウム燃料は、ウランに比べて中性子を吸収しやすく(核分裂しやすく)、そのため核暴走が起こりやすく、核暴走のスピードも大きい。
フランスの高速増殖炉フェニックスでは、たびたび核分裂反応の暴走事故が発生し、出力上昇が100分の5秒という短時間に起こりながら、いまだに原因が解明されていない。
しかも、このような核暴走に対して、増殖炉では制御棒のほかに対策がなく、軽水炉に備えられている緊急炉心冷却装置(ECCS)さえ持たない。
□アメリカの高速増殖炉では炉心溶融事故を2度も起こしているが、わずかでも炉心溶融が起これば、プルトニウム濃度がその部分で高まり、急速な臨海反応によって原子炉が原爆化する可能性があります。
□燃料からから熱を奪うために使われるナトリウムは、金属パイプの壁一枚を隔てて、発電用として水蒸気を発生させる水と隣り合っています。このナトリウムは、水とはんのうして爆発炎上し、高温では空気とも反応して炎上する性質があります。
さらにナトリウムの腐食性が大きいので、配管事故が起こりやすく、伝熱パイプに亀裂が生じたり破損すれば、たちまち爆発に進展する可能性が高い。
イギリスでは1987年2月、高速増殖炉PFRで、蒸気発生器の細管ギロチン破断事故が発生し、40本の細管を連続破断させるドミノ倒し現象が起こり、かろうじて大惨事を免れた。
□軽水炉の水蒸気温度が300度であるのに比べて、増殖炉ではナトリウムが500度以上、水蒸気温度も500度近い温度であります。
この高温は、原子炉の停止時と運転時に、配管を大きく膨張・収縮させ、しかも伝熱パイプの内側と外側の圧力差は、130気圧ときわめて大きい。
このような厳しい条件にさらされるため、ごくわずかな金属欠陥があるだけで大事故を誘発しやすく、特に、高速増殖炉で使われる薄く大口径の配管は、地震に対してほとんど無力なのです。
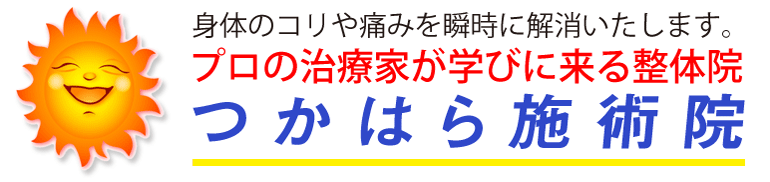




愛がガンを消した!? 奇跡は連鎖する by 韮沢香織 (04/19)
2015年1月スケジュール by 1 (01/11)
日曜日の朝にリフレッシュ!!高橋リサ先生と「朝ヨガと巨石パーク」 by マック (09/16)
日曜日の朝にリフレッシュ!!高橋リサ先生と「朝ヨガと巨石パーク」 by ちろる (09/16)