産経新聞yori
田中秀幸料理長が考案した薬膳の加齢臭対策メニューから。手前は市販のチルド麺を使い、肝臓の働きを助ける野菜をたっぷり加えた「焼きそば」。奥の「赤魚の酒蒸し」は抗酸化力の強い食材を組み合わせた一品
中高年特有の体臭「加齢臭」。陽気がよくなり、薄着になると気になる人も多いのでは。加齢臭は不快なにおいというだけでなく、「生活習慣病のサイン」ともいわれる。体を清潔に保つことが大切だが、普段の食生活で体の内側から改善することも必要だ。(榊聡美)
加齢臭が出ている?ゴリと合唱する夏帆
≪生活習慣病と同じ≫
まず、加齢臭はどのように発生するのだろうか。
加齢臭の原因はノネナールと呼ばれる物質。ノネナールは皮脂腺から分泌される「9−ヘキサデセン酸」という脂肪酸が、皮膚の常在菌などにより化学変化を起こしてつくられる。この脂肪酸は年齢とともに増加し、また中高年になると、過酸化脂質が増えて化学変化を起こしやすくなることが解明されている。
『40代からの気になる口臭・体臭・加齢臭』(旬報社)を監修した五味クリニックの五味常明院長は「血管の中にコレステロールが蓄積されるのと同じように、皮脂腺にも脂肪分が増える。脂肪分が多くなれば、ノネナールの量も多くなる」と話す。
暴飲暴食や動物性脂肪の摂りすぎといった不摂生な食生活は、皮脂腺から出る脂肪酸の量を増やし、また喫煙やストレスの多い生活は過酸化脂質を増やすことから、加齢臭を強くする。ちょうど生活習慣病につながる要因が、ノネナールを増やす原因になっているのだ。五味院長は「急に加齢臭が強くなったり、若いうちから加齢臭が出たりするのは注意すべきです」と指摘する。
ノネナールを減らすためには、体の内側からの対策が必要だ。それには、まず皮脂腺の脂肪酸の原因となる肉類、バターなど、脂質の摂取を抑えること。そして抗酸化作用のある食べ物を意識的に摂ること。主な抗酸化物質は、ビタミンC・E、大豆製品に含まれるイソフラボン、ゴマのセサミノールなどが挙げられる。このほか、梅干しや海藻類、それにワサビなどの薬味も有効だという。
五味院長が勧めるのはずばり、和食。「古くは仏教では体から出るにおいは不浄とされていたため、精進料理は体臭を抑える食材が使われていた。つまり、和食は“食べる消臭剤”なのです」と説明する。
≪薬膳で体質改善≫
「加齢臭を抑えるには、酸化しにくい『抗酸化体質』を目指すことが肝心です」。こう話すのは、国際薬膳調理師の資格をもつ、虎ノ門パストラルホテル(東京都港区)の中国料理「天壇」の田中秀幸料理長。「手軽にできる薬膳(やくぜん)の加齢臭対策メニューを考えてみました」
まず一品目は、目にも鮮やかな「赤魚の酒蒸し」。真ダイと、パプリカ、グリーンアスパラガスなどの野菜を組み合わせ、オイスターソースをベースにした合わせ調味料を加え、電子レンジで調理する簡単メニュー。「色のきれいなものは抗酸化効果が高い」と田中料理長。
次に食卓の定番「焼きそば」。肉類を使わず、肝臓の働きを助け、デトックス(解毒)効果が期待できるレタス、キャベツ、ブロッコリーなどの野菜をたっぷりと使い、仕上げにのりを散らすのがミソだ。
加齢臭は男性特有のものではない。気になり始めたら、食生活を見直してみてはいかがだろうか。
田中秀幸料理長が考案した薬膳の加齢臭対策メニューから。手前は市販のチルド麺を使い、肝臓の働きを助ける野菜をたっぷり加えた「焼きそば」。奥の「赤魚の酒蒸し」は抗酸化力の強い食材を組み合わせた一品
中高年特有の体臭「加齢臭」。陽気がよくなり、薄着になると気になる人も多いのでは。加齢臭は不快なにおいというだけでなく、「生活習慣病のサイン」ともいわれる。体を清潔に保つことが大切だが、普段の食生活で体の内側から改善することも必要だ。(榊聡美)
加齢臭が出ている?ゴリと合唱する夏帆
≪生活習慣病と同じ≫
まず、加齢臭はどのように発生するのだろうか。
加齢臭の原因はノネナールと呼ばれる物質。ノネナールは皮脂腺から分泌される「9−ヘキサデセン酸」という脂肪酸が、皮膚の常在菌などにより化学変化を起こしてつくられる。この脂肪酸は年齢とともに増加し、また中高年になると、過酸化脂質が増えて化学変化を起こしやすくなることが解明されている。
『40代からの気になる口臭・体臭・加齢臭』(旬報社)を監修した五味クリニックの五味常明院長は「血管の中にコレステロールが蓄積されるのと同じように、皮脂腺にも脂肪分が増える。脂肪分が多くなれば、ノネナールの量も多くなる」と話す。
暴飲暴食や動物性脂肪の摂りすぎといった不摂生な食生活は、皮脂腺から出る脂肪酸の量を増やし、また喫煙やストレスの多い生活は過酸化脂質を増やすことから、加齢臭を強くする。ちょうど生活習慣病につながる要因が、ノネナールを増やす原因になっているのだ。五味院長は「急に加齢臭が強くなったり、若いうちから加齢臭が出たりするのは注意すべきです」と指摘する。
ノネナールを減らすためには、体の内側からの対策が必要だ。それには、まず皮脂腺の脂肪酸の原因となる肉類、バターなど、脂質の摂取を抑えること。そして抗酸化作用のある食べ物を意識的に摂ること。主な抗酸化物質は、ビタミンC・E、大豆製品に含まれるイソフラボン、ゴマのセサミノールなどが挙げられる。このほか、梅干しや海藻類、それにワサビなどの薬味も有効だという。
五味院長が勧めるのはずばり、和食。「古くは仏教では体から出るにおいは不浄とされていたため、精進料理は体臭を抑える食材が使われていた。つまり、和食は“食べる消臭剤”なのです」と説明する。
≪薬膳で体質改善≫
「加齢臭を抑えるには、酸化しにくい『抗酸化体質』を目指すことが肝心です」。こう話すのは、国際薬膳調理師の資格をもつ、虎ノ門パストラルホテル(東京都港区)の中国料理「天壇」の田中秀幸料理長。「手軽にできる薬膳(やくぜん)の加齢臭対策メニューを考えてみました」
まず一品目は、目にも鮮やかな「赤魚の酒蒸し」。真ダイと、パプリカ、グリーンアスパラガスなどの野菜を組み合わせ、オイスターソースをベースにした合わせ調味料を加え、電子レンジで調理する簡単メニュー。「色のきれいなものは抗酸化効果が高い」と田中料理長。
次に食卓の定番「焼きそば」。肉類を使わず、肝臓の働きを助け、デトックス(解毒)効果が期待できるレタス、キャベツ、ブロッコリーなどの野菜をたっぷりと使い、仕上げにのりを散らすのがミソだ。
加齢臭は男性特有のものではない。気になり始めたら、食生活を見直してみてはいかがだろうか。
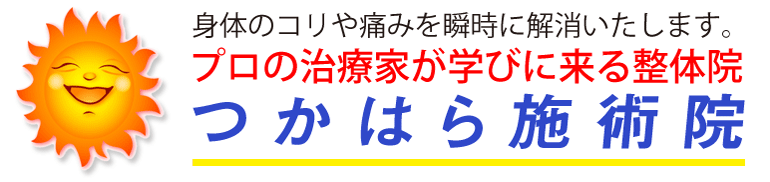




愛がガンを消した!? 奇跡は連鎖する by 韮沢香織 (04/19)
2015年1月スケジュール by 1 (01/11)
日曜日の朝にリフレッシュ!!高橋リサ先生と「朝ヨガと巨石パーク」 by マック (09/16)
日曜日の朝にリフレッシュ!!高橋リサ先生と「朝ヨガと巨石パーク」 by ちろる (09/16)