ここ数日、ブログ更新をしなくてごめんなさ〜いヾ(_ _。)
全国の女性ファンが、悲しんでいたのではないでしょうか(笑)
今日もちょっと忙しくてっていうか、お客様との間の空いた時間のタイミングが合わなくて更新できませんでした。
今回はそういうことで、パクリです。
NIKKEIネットより
アボリジニの教訓
西欧化した食習慣で激増した生活習慣病
WHO(世界保健機関)と協力して私どもの国際共同研究センターではここ3年にわたり、もっとも健康状態が悪く文化的・社会的に調査協力を求めるのが困難な地域の調査を手がけています。そうした地域では、早急に健康問題に対処しなければ、民族存亡の危機にあるといっても言い過ぎではない状況があるからです。そして、それらの問題から引き出せることは、近代化が進み都市生活をおくるようになり食環境が変わってきた地球上のすべての人々の健康問題にもあてはまることです。
■
50代で100パーセントが生活習慣病に
オーストラリア先住民族アボリジニの調査では、40代になると3人に2人が肥満と糖尿病または、高血圧。50代前半になると90パーセント、50代後半ではほぼ100パーセントがいずれかの病気になっていました。そして、平均寿命は白人に比べると20年近くも短命という驚くべき実態でした。
■
倹約遺伝子で塩、砂糖がなくても元気な体質
アボリジニは19世紀まで狩猟採集の生活をしていて、食塩や砂糖、油脂、スーパーマーケットなどで売られているような加工食品とは無縁でした。それらを充分食べない状態でも元気に生きていけるような「倹約遺伝子」のおかげで生きのびてきた民族なのです。
■
塩分や砂糖、油脂を食べるようになると反応する倹約遺伝子
アボリジニは、オーストラリアの歴史が語るように自らのライフスタイルを捨てさせられてしまった民族です。都市で生活することを余儀なくされてしまった人々は、加工食品や料理などから食塩や砂糖、油脂を否応なく食べるようになってしまいました。食塩や砂糖、油脂などが少なくても健康に生きていけるよう働いていた倹約遺伝子は、食塩を少し多く食べるようになると高血圧に、砂糖(炭水化物)や油脂は、肥満や糖尿病にむすびつくように働いてしまいます。そうして、アボリジニの人たちは、たちまち生活習慣病を多発するようになってしまったのです。
アフリカのマサイ族も塩には無縁(無塩)でしたが、マーケットが開かれるような村で生活する部族では、食塩の摂取量が増え、また糖や油脂も多く食べるようになり、高血圧や肥満などの生活習慣病が増えていました。
かつて長寿の村として有名であったエクアドルのビルカバンバなどでも同じようなことが起こっています。
■
都市生活者が増加した日本人の場合
こうした、生活習慣病とは無縁だった民族で、食環境の変化により起こる問題は、現在の日本人が抱える問題と本質的に同じなのです。
日本人は、摂取エネルギーが少ない状態で生きてきた民族です。食事が欧米化し、動物性脂肪分や糖分が多い食生活になるとエネルギーが体質にしては過剰な状態がつづき、糖尿病や高血圧になりやすくなります。
遺伝的要素に食環境の変化が加わると生活習慣病になります。見方を変えると「生活習慣病は食生活の改善で予防できる」と言えるのです。
要注意! 30歳以上の4割は高血圧
さっそく、日本のデータを見てみましょう。左のグラフは、厚生労働省が30歳以上の男女を対象に行った調査によるものです。男性では30歳代から高血圧と診断される人は、4割を超え、40歳代からは半数以上の人が高血圧になっています。女性でも30歳代から高血圧になる人が増える傾向にあります。
男性が女性よりも高血圧になりやすいのは女性ホルモンが少ないためです。
■
頼りになる大豆イソフラボンのパワー
大豆イソフラボンは、女性ホルモンと似た作用をします。毎日50mg食事から摂っている地域では、高血圧も関係する心筋梗塞死亡率が少ない事が、私どもの世界25ヵ国60地域の研究で明らかになっています。
「高血圧」ってなに? 自分の血圧をチェックしてみよう
高血圧と診断されるのは、血圧を測って上の数値が140mmHg以上、下の数値が90mmHg以上になった状態です。
上の数値は収縮期血圧と言い、心臓が収縮して全身に血液を送るときの血圧。下の数値は拡張期血圧といって心臓に血液が流れ込んで膨らむ時の血圧です。
血圧が140/90以下の「正常な血圧」のうち上図の★印の範囲は「正常高値血圧」で注意が必要。糖尿病やコレステロール値が高い場合や喫煙、遺伝など危険因子を持つ場合は、この段階から治療が必要とされることもあります。
また、高血圧が軽症でも、あわせ持っている危険因子(糖尿病や高コレステロール血症、心臓病など)の種類や数で危険度は異なりますので注意しましょう。
高血圧の原因は? 生活習慣がカギ
高血圧には2種類あります。そのうち原因が特定できるのは腎臓の病気(腎炎や腎盂炎など)や内分泌系の病気(副腎の腫瘍や甲状腺機能亢進症など)が原因となって起こる二次性高血圧です。特別病気がないのに血圧が高くなるのが本態性高血圧。生活習慣の乱れや遺伝、加齢などさまざまな要因が重なって血圧が高くなります。原因をひとつに特定できない場合が多く、全体の95%、あるいはそれ以上を占めています。
「タバコも吸っているし、運動も殆どやらない。父や母などが高血圧で自分も遺伝で高血圧、塩分を控えてもダメだ」と言った考えは間違いです。本態性高血圧は、生活習慣の改善で予防または、改善できることがこれまでの研究でわかっています。
血圧が高いと脳卒中や心筋梗塞による死亡率が高まる
高血圧の状態が続くと血管の壁が次第に変化して動脈硬化が進行します。その様子は下図のようになります。高血圧に加えて糖尿病やコレステロール値が高い高脂血症などをあわせ持っていると動脈硬化の進行は早くなります。(重要情報:黒豆茶や野菜・果物の抗酸化栄養素は悪玉コレステロールの酸化を抑え、動脈硬化を防ぐ役割をします)
肥満、高脂血症、糖尿病、高血圧で「死の四重奏」
放っておくと命を落とす高血圧の合併症
肥満の序曲が始まり、糖尿病、高脂血症、高血圧の4点セットは、心筋梗塞や脳卒中になりやすく、死の四重奏といわれています。血圧が高いと全身の血管に負担がかかり、脳梗塞、狭心症,心筋梗塞、腎不全などさまざまな病気に進展し、命にかかわる場合や重い合併症をもたらします。
まとめ
■
危険因子を知って生活習慣を見直そう
多くの高血圧は、遺伝的要因に生活習慣がかかわって発症します。私どもの研究で明らかにしてきた高血圧のリスクは、食塩のとりすぎ、肥満、栄養バランスの乱れ(たんぱく質、マグネシウム、カリウム、カルシウム不足など)、飲酒(注-1)コレステロール過多、糖尿病(注-2)などです。また、運動不足、ストレス過多、喫煙などもあげられます。
また、男性は女性に比べて女性ホルモンが少なく50歳をすぎ、図のような危険因子をもつと高血圧になりやすくなります。
いま一度生活習慣をチェック。そして、大豆食品や魚介類、野菜・果物を食べ、塩分とりすぎに注意をして高血圧を予防しましょう。
(注-1) 1週間に純アルコール換算300mlで血圧が上昇。ビールならば約1日に350ml缶×3本でオーバー、2本でセーフ。 日本酒の場合、約1,5合以内が目安。
(注-2) 糖尿病になってしまっても血圧が上がらないことも多い。高血圧と関係するのは?型糖尿病。インスリンがききにくくなり、過剰に分泌されつづけると肥満になり、ナトリウム貯留や交感神経の亢進がおこり血圧が上昇しやすい。
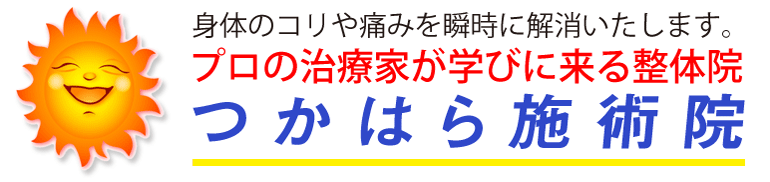




愛がガンを消した!? 奇跡は連鎖する by 韮沢香織 (04/19)
2015年1月スケジュール by 1 (01/11)
日曜日の朝にリフレッシュ!!高橋リサ先生と「朝ヨガと巨石パーク」 by マック (09/16)
日曜日の朝にリフレッシュ!!高橋リサ先生と「朝ヨガと巨石パーク」 by ちろる (09/16)